こんにちは、はやみです。
子どもがADHDグレーゾーンといわれたら、驚いたり納得したり、さまざまな感情がわいてきますよね。
ADHDってなに?から始まり、さらにグレーゾーンってなに?
特性を理解して関わりましょう?
「?」だらけですよね。
我が家の長男がADHDグレーゾーンといわれたのが年中の春でした。
担任の先生から発達相談をすすめられ、発達検査を受けたのがきっかけです。
「クラス内で立ち歩きや急な大声があり目立つ」
「見通しがたたないと不安になる」
「座る場所がわからなくてパニックになる」
育てにくさは感じていましたが、正直驚きました。
年中になり発達検査を受けたところ、「ADHDの傾向はあるが、確定診断はできない」という結果に。
それ以降、ADHDグレーゾーンという解釈で育児をしています。
保護者が知識を増やして、子どもの特性を理解することで、子どもの行動はガラッと変わります♪
まずは、ADHDについての理解を深めていきましょう。
ということで今回は、以下の疑問にお答えします。
・ADHDってなに?
・ADHDグレーゾーンってどういう意味?
ADHDってなに?

ADHDは、発達障害の1つです。
発達障害とは生まれつきの特性で、ADHDの特徴は「不注意」と「多動性・衝動性」といわれています。
発達年齢に比べて、落ち着きがない、待てない(多動性-衝動性)、注意が持続しにくい、作業にミスが多い(不注意)といった特性があります。多動性−衝動性と不注意の両方が認められる場合も、いずれか一方が認められる場合もあります。
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_develop.html
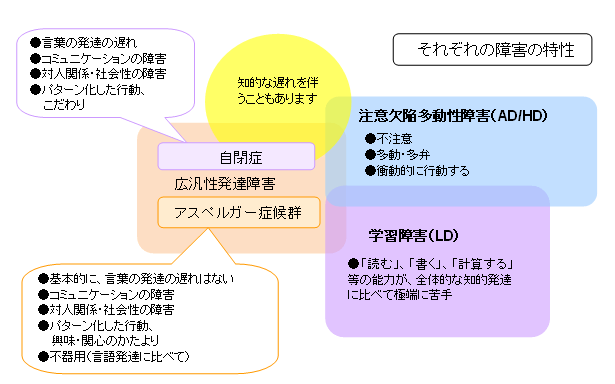
上記の表のように、発達障害にはそれぞれの特性があります。
ADHDの特性について、詳しくみていきましょう。
ADHDの主な特徴は、「不注意」「多動性」「衝動性」
ADHDの特徴は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つにわけることができます。
一言でいえば、「そそっかしい」ということ。
気が散りやすく、集中しているのが苦手。うっかりミスが多い、よく忘れ物をする、聞いていたはずの話を覚えていないといった特徴がみられる。
よく動き、落ち着きがない。座っていても手足や上半身が動く、順番をじっくり待てない、じっと集中して勉強するのが苦手といった特徴がみられる。
思いついたら行動してしまう。気になるものをみつけると授業中でも立ち歩く、急に発言する、思いつきで話すので会話が食い違うといった特徴がみられる。
日常的にそそっかしさが強く、そのせいで困りごとがあると考えると理解しやすいですね。
引用:本田秀夫、日戸由刈(2017)
ADHDの子の育て方のコツがわかる本
講談社
ADHDグレーゾーンってどういう意味?

ADHDグレーゾーンとはどういう意味なのでしょうか。
結論からいうと、「診断はつかないけれど、ADHDの傾向がある」という状態です。
ADHDの特性がいくつかみられるけれど、診断基準をすべて満たしてはいないため、確定診断ができないということですね。
なので、ADHDの診断基準については知っておいたほうが良いでしょう。
ADHD(注意欠如・多動症)の診断基準
ADHD(注意欠如・多動症)の診断には、「不注意」と「多動性・衝動性」の症状をチェックする方法が用いられます。
- 勉強中に不注意な間違いをする
- 活動中に注意を持続することが困難
- 話を聞いていないように見える
- 指示に従えず勉強をやり遂げられない
- 課題を順序立てることが困難
- 精神的努力が必要な課題を嫌う
- 必要なものをよくなくす
- 外的な刺激によってすぐ気が散る
- 日々の活動で忘れっぽい
- 手足をそわそわ動かす
- 席についていられない
- 不適切な状況で走り回る
- 静かに遊べない
- じっとしていない
- しゃべりすぎる
- 質問が終わる前に答え始める
- 順番を待つことが困難
- 他人を妨害し、邪魔する
※9項目のうち6項目以上みられ、6カ月以上継続し、家庭での生活や学校での活動に困りごとがある場合、ADHDの可能性が考えられます。
参考:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_347.html#topic2
https://adds.or.jp/sodan/post-390/
ADHDグレーゾーンでは、これらの症状がいくつかはあてはまることになります。
大切なのは、子どもがどういう場面でどんなことに躓くのかを把握し、早い段階で原因を発見してケアすることです。
まとめ
さいごにまとめです。
- ADHDの特徴は、「不注意」「多動性」「衝動性」
- ADHDグレーゾーンとは、診断基準は満たしていないが、ADHDの傾向がある状態のこと
ADHDは生まれつきの特性であり、日常生活にどれぐらい支障があるのかが診断基準となります。
ADHDグレーゾーンの場合は、ADHDの傾向がある状態です。
「そそっかしさ」や「うっかり」が生活上の支障にならないように、子どもを観察し適宜対応することが重要です。



コメント